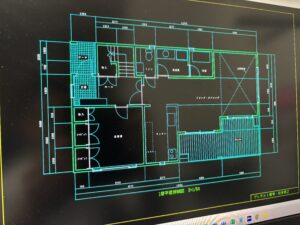民泊を始めるには?必要な手続きと注意点を行政書士が解説
「空き部屋を有効活用したい」
「副収入を得たい」
といった理由から、
民泊を始めたいと考える方が増えています。
しかし、
民泊はただ人を泊めればいいというわけではなく、
法令に基づく手続きや基準のクリアが必須です。
今回は、
民泊を始める際に必要な手続きや注意点について、
行政書士の視点からめっちゃ分かりやすく解説します。
◆民泊には3つのタイプがある
まず、「民泊」といっても、
実は大きく分けて次の3種類があります。
1.住宅宿泊事業(民泊新法)
2.旅館業法に基づく簡易宿所営業
3.特区民泊(国家戦略特区)
どの制度を使うかによって、
申請先や要件が異なります。
以下でそれぞれの概要と
手続きの流れを見ていきましょう。
◆1.住宅宿泊事業(民泊新法)による民泊
<特徴>
・年間180日までの営業が可能
・届出制(許可ではなく届出)
<手続きの流れ>
1.自治体への届出(オンラインまたは書面)
2.必要書類の提出(間取り図、設備、本人確認書類など)
3.消防・衛生に関する基準の確認
4.近隣住民への事前説明や掲示義務
5.住宅宿泊管理業者との契約(必要な場合)
<注意点>
180日制限があるため、通年営業は不可。
地域によっては条例で営業が制限されていることがあります。
◆2.旅館業法の簡易宿所営業による民泊
<特徴>
・年間営業日数の制限なし
・許可制(保健所の許可が必要)
<手続きの流れ>
1.建築基準法・消防法に適合した施設整備
2.保健所への事前相談
3.簡易宿所営業の申請
4.現地検査
5.営業許可の取得
<注意点>
玄関帳場の設置、避難経路、
トイレ数など厳しい構造要件あり。
建築基準法の「用途変更」が必要な場合もあります。
◆3.特区民泊(国家戦略特別区域)
<特徴>
・特定の地域(例:大阪市・東京都大田区など)のみで実施可能
・滞在期間が2泊3日以上などの条件あり
<手続きの流れ>
1.自治体への申請
2.要件を満たす施設・設備の整備
3.地域によって独自の基準・ルールあり
<注意点>
対象地域に限られている。
民泊新法よりも柔軟な制度だが、自治体によって基準はまちまち。
◆民泊を始める前に確認すべきポイント
・建物の用途地域・管理規約の確認(分譲マンションの場合)
・近隣住民とのトラブル防止対策
・消防設備の設置義務
・保健所や行政との事前相談
◆行政書士がサポートできること
民泊の手続きは、
建築・消防・衛生と多岐にわたります。
行政書士は以下のようなサポートが可能です。
・住宅宿泊事業の届出代行
・簡易宿所営業許可の申請サポート
・必要図面(間取り図など)の作成
・関係官公署との事前協議
・管理規約や利用規約の整備
◆まとめ
民泊を始めるには、
どの制度を使うかをまず決め、
それに応じた手続きと施設の整備が必要です。
適切な制度を選び、
トラブルを避けて安心・安全な運営を行うためにも、
専門家のサポートを受けることをおすすめします。
<無料相談受付中>
ステイブル行政書士オフィスは、
深夜酒類提供飲食店営業の届出に必要な図面の作成・チェックをはじめ、
申請書類の作成から警察署とのやりとりまで、
トータルでのサポートを提供しています。
・お店の測量から図面作成もOK
・面倒な用途地域の確認や届出書作成もお任せ
・オンライン相談にも対応しています
ぜひお気軽にご連絡をください。
その他、飲食店営業許可、深夜酒類提供飲食店営業届出、図面作成代行サービスの詳細はこちら
今後も飲食店営業許可、風俗営業関連、
キャッシュレス決済導入に役立つ情報を発信していきます!
使用画像:
UnsplashのFilios Sazeidesが撮影した写真
この記事を書いた人:行政書士 松本 英之
ステイブル行政書士オフィスでは、これから飲食店を開業するために必要な、飲食店営業許可申請(保健所)や深夜の酒類提供の届出(警察署)の書類作成、代行サービス、キャッシュレス業界の表と裏を知る行政書士が、店舗のキャッシュレス対応のアドバイス、コンサルティングも行っております。申請に必要な図面作成の代行サービスもあります(建築CAD検定資格保持)。